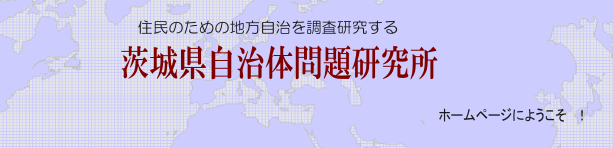FrontPage
2024・04・24更新


国営ひたち海浜公園=ひたちなか市
国営ひたち海浜公園みはらしの丘に咲くネモフィラは、春の訪れを告げる美しい花。丘一面を青く染めるネモフィラは4月中旬から5月上旬が見ごろ。ネモフィラは、英名では「baby blue eyes」。約4.2ヘクタールの丘一面が約530万本のネモフィラで埋め尽くされる。
ー 今国会における地方自治法改正案の危険 ―
政府が非常時に自治体に指示する権限を導入
地方自治法の改正案が今国会に提出されている。改正法案のポイントは次の4点。
◎非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができる。◎閣議決定を経るのが条件。◎自治体は指示に応じる法的義務を負う。◎国が非常時への対処方針を検討する際、自治体に資料の提出を求められる。
地方からは、「指示が乱発されれば地方の自主性を損なう」と懸念を示している。
高知新聞は社説で(2024年3月10日付)、【国の指示権拡充】地方自治をゆがめないか、との表題の下次のように警戒している。
国の指示権は現在、災害対策基本法など個別法に規定があれば行使できるが、発動の可能性は最小限に抑えられている。改正案はその要件を緩め、個別法に規定がなくても「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と国が判断すれば、指示権を使えるようにする。
想定外の事態が起きた時の混乱を防ぐため、あらかじめルールを設ける発想は否定しない。ただ、2000年施行の地方分権一括法は、国と自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に変えた。分権の流れを巻き戻す動きになる。「指示が必要な事態」を国の都合のよいように解釈すれば、地方の主体性や自立性がゆがめられる危険もはらむ。国会審議では丁寧な議論と慎重な判断が求められる。
政府は法制化に当たり、厳格な運用を強調。指示権発動は国と地方の対等関係の中での「特例」と位置づけたほか、発動前には自治体に意見聴取し、閣議決定を経るなどといった手続きも盛り込んだ。
しかし、発動要件となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の定義はあいまいで、やはり拡大解釈、指示権乱用の懸念が残る。政府の「厳格な運用」との説明が懐疑的に聞こえてしまうのは、今の政府・与党は、非常時の国の権限強化に躍起になってきたからだ。
緊急事態条項の新設を目指す憲法改正論議に象徴されるように、緊張感を増す安全保障環境を理由に、中央集権的な国づくりを進めているように映る。米軍普天間飛行場の移設問題を巡り、沖縄県の民意を押し切って工事に着手したのもその一例ではないか。
非常措置に固執している岸田政権の提起だけに、いくら警戒してもし過ぎることはない。
今月の俳句
花冷えや少女に重きランドセル
本流にのりて安らぐ流し雛
クレーンが鉄骨を吊る春夕焼
信号の赤あざやかに春疾風(はるはやて)
薬飲み忘れし午後の草朧(くさおぼろ)
高 島 つよし
本名 高島剛 常総市在住、句歴七十年 元茨城県職員 元小貝保育園長、当研究所顧問
寄 稿
1県1水道の問題点をひた隠しにする茨城県
~資料の全面公開を求める
田中 真己(水戸市議会議員)
1.強引に事を進める茨城県
私達は茨城県が推進する1県1水道、経営一体化について、水道料金値上げや、7割もの浄水場の廃止で災害リスクを高めるとして反対してきた。
水道広域化や経営統合のねらいは、官民連携の名のもとに、水道事業の運営を民間に開放することを見越したものである。
さらに、これまでのムダな水源開発の反省もなく、市町村の自己水源を閉じさせて、高い県の水を買わせようというものである。
茨城県は推進姿勢をくずさず、離脱を表明した水戸市以外の自治体からなる「広域連携検討・調整会議」で、令和6年度中にも経営統合や県水道との一体化の検討・シミュレーションを進める方針である。今後、一体化を決断した自治体とは法定協議会が結成され、一気に統合に進む危険がある。
2.7割の浄水場廃止の水道広域化プラン~徹底した情報公開を求める
茨城県内の水道事業は、県北・県中央・鹿行・県南・県西の5つの圏域に分かれている。県は水道広域化プランで、県内105ある浄水場のうち70か所を閉鎖し、35まで削減しようとしている。しかし、どの自治体のどの浄水場を閉鎖するかは示していない。
能登半島地震でも水道の断水が深刻な問題となっているなか、身近な浄水場を閉鎖することがいかに危険なことか、住民に広く知らせる必要がある。
私は、閉鎖する浄水場の具体名やシミュレーションの根拠などの情報公開を請求したが結果はほぼ黒塗り、いわゆる「のり弁」の資料しか出されなかった。
そのため昨年10月、黒塗り資料の全面公開を求め知事に行政不服審査法に基づく「不服審査請求」を提出した。11月に県から「弁明書」が届いたが、あまりにひどい内容だったため、再度11月28日付けで「反論書」を提出した。
今後、弁護士や大学教授など10人の委員で構成された「情報公開・個人情報保護審査会」で、開示・不開示決定の当否が審査される。
しかし、今年3月末に県情報公開室に「いつ判断が出るのか」と問い合わせたところ「審査会の案件が10本程度たまっており、審査は半年くらい先の見込み」という驚くべき返事だった。一体なんのための審査会なのか、ずるずる審査を遅らせて、公開請求の意欲をなくさせる作戦か。情報公開制度が全く機能していないと言わざるをえない。
3.黒塗りには不当~「反論書」で主張
県は弁明書で「不開示情報を公にすると、施設の統廃合や給水原価に対する誤解や憶測に基づき、災害時の対応や水道料金の値上げに関する不安が生じるなど、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがある」としている。
しかし、広域化推進プランは「経営一体化で合理化すれば、各自治体が単独経営を続けるよりも給水原価の上昇を抑制できる」と効果を強調している。
単独経営よりも広域化した方が値上げ抑制効果があるとしながら、「値上げに関する不安を生じるから開示しない」というのは自己矛盾に陥った説明がつかない態度である。
また、県は「検討中の情報は公表すべきでない」というが、シミュレーションの結果は「広域化推進プラン」として現に公表されている。
結果が公表されていない段階で、検討途中のシミュレーションの数値が公表されれば「誤解や憶測に基づき混乱を生じさせるから開示できない」と言うのならばともかく、県が自ら公表したシミュレーション結果の根拠すら公表しないのでは、説明責任を果たさない不当な態度というほかない。
さらに、県は「各水道事業体の経営戦略や個別の方針や計画を反映したものではない」というが、個別の状況を反映しないようなプランで具体的取組を進めようとしているのか。根拠も開示できないのでは「検証に耐えられないずさんプランだ」と県みずから認めたも同然である。
さらに、広域化推進プランには2つの重大問題が欠落している。一つは、全国一高い県中央広域水道の料金をどうするのか、二つはムダな水源開発である霞ケ浦導水事業についてである。導水事業完成後に発生する市町村の莫大な負担を示さないまま、なぜ「経営の一体化は単独経営より給水原価を下げられ費用抑制効果が得られる」といえるのか説明すべきである。
4.ライフラインの水道を守れ~住民を敵視する県に水道事業を担う資格なし
水道事業は重要なライフラインであるから県民が自分の住む自治体の水道事業がどうなるのか知りたいと考えるのは当然なのに、県民からの「苦情や干渉が増える」と言って情報開示しないのは、県民を敵視する考え方である。
物価高騰が続く中で水道料金はどうなるのか、災害時も含めて水道が今後も安定供給されるのかなど、県民の関心や不安が高まっている。
だからこそ水道事業は住民の意向を十分に反映した運営を行うべきであり、むしろ要望が多く寄せられることは民主的な手続きを踏んだ行政運営をするうえで当然のことである。
命の水を守り、持続可能な水道事業を作り上げていくためには、きちんとした現場の分析や水道事業を維持するための県民や議会の理解が必要である。
地方自治法は「住民こそが自治の担い手である」という観点から、各種権利を住民に認めている。にもかかわらず、住民や議会から出される意見を「苦情」や「干渉」と捉える県の弁明書は、もはや地方自治法に逸脱していると言わざるをえない。単独経営と広域化それぞれのメリットやデメリット、リスクも含めて県民に広く情報を開示し、説明し合意を得るべきなのに、なるべく情報を開示せず「秘密裏に方針を決定した後に知らせればよい」という県の考え方は、時代遅れで民主的とは言えない。
以上のことから、私は「開示を求めている情報は、正確な事実に基づいて判断するために最低限必要な情報であって、公表したからといって市町村等の意思決定を混乱させることにはならない。よって再度、全面開示を求める」と主張した。
引き続き徹底した情報公開と、議会や住民への説明を求めるとともに、ライフラインである水道をズタズタにし、水道料金値上げにつながる広域化に反対をつらぬいて奮闘する決意である。
以 上
************
寄 稿
結成総会開催
八ッ場ダムストップさせる茨城の会から茨城県の水問題を考える市民連絡会へ
関戸 勇(茨城県の水問題を考える市民連絡会事務局長)
茨城県の水問題を考える市民連絡会の結成総会が2月15日午後、取手市の福祉会館で開かれました。総会には県内から25名が参加しました。
総会では、八ッ場ダムストップさせる茨城の会の神原事務局長が経過報告を行い、
茨城県が2022年に出した「茨城新水道ビジョン」について、県が大幅に水が余っている状況でもハッ場ダムをつくり、更に膨大な余剰水を抱える霞ヶ浦導水事業の整合性をとるため、茨城県内の行政が独自に運営している水道事業(簡易水道も含め)を全て止めさせ、県が作る水道水を買わせようとする水道の一元化で、水道料金の平準化、つまり水道料金の値上げに結びつくとんでもない計画であることを報告しました。
総会は八ッ場ダムストップさせる茨城の会から茨城県の水問題を考える市民連絡会という新たな運動体への移行を提案し了承されました。また総会では、運動を担う役員体制について提案、12名の役員が選出されました。
「茨城県の水問題を考える市民連絡会」は県内全域、特に北部など自下水源で水道事業を運営し、供給を受ける市民や団体を結集、茨城県の水道事業の転換を求めます。連絡会は最初の取り組みとして6月30日(日)午後2時より土浦駅西口の「県南生涯学習センター」(ウララ)で「茨城県の水道ビジョン」について学習会を計画しました。ぜひ参加下さい。
茨城県の水道ビジョンを問う
暮らしに重い負担となる・1県1水道政策
水問題学習会 6月30日(日)午後2時~
講 師:神原禮二 (八ッ場ダムストップ茨城の会元事務局長)
会 場:県南生涯学習センター 講座室 (ウララ 土浦駅前の市役所と同じビル)
参加費:資料代として100円
主 催:茨城県の水問題を考える市民連絡会
イベント紹介
第28回全国小さくても輝く自治体フォーラム in 木城町
『ないないの町』 宮崎県木城町で、小さくても輝く町村づくりを学び、共に考える
「全国小さくても輝く自治体フォーラム」は、自律をめざす小規模自治体の維持と発展をはかることを目的とした交流の場です。「平成の大合併」が呼びかけられていた平成15年に第1回を開催し、平成22年に恒常的な会員組織「全国小さくても輝く自治体フォーラムの会」を設立し今日に至つています。
このたび第28回となるフォーラムを宮崎県本城町で開催します。県の中央に位置し、面積の84%は山林原野が占める緑豊かな木城町は、「鉄道ない!国道ない!ないないの町で、僕も生きる!」を掲げ、「人が元気、地域が元気、住んで良かつた」と実現できる町づくりを町民参加で豊かに実践されています。
本城町を含む宮崎の町村の魅力と取り組みに学ぶとともに、創造的な取り組みで、小さくても輝く町村を築いてきた全国の取組を参加者相互に学びましよう。多くの参加をお待ちしています。
開催日:令和6(2024)年5月10日(金)~11日(土)
会場:宮崎県木城町 木城町立総合交流センター(木城町大字椎木2146-1)他
主催: 全国小さくても輝く自治体フォーラムの会
事務局 自治体問題研究所〒162-8512新宿区矢来町123矢来ビル4階
FAX 03-3235-5933 TEL03-3235-5941 E-mail info@jichiken.jp
令和6年5月10日(金)
13:45-14:00 開会挨拶
小坂泰久会長開催地挨拶、半渡英俊木城町長
14:00-14:30 ミニ講演「『地方分権』から『中央集権』への逆流~地方自治法改正の概要と問題点(仮)」
白藤博行・専修大学名誉教授
14:30-15:20 記念講演「自律と支え合いによる地域の再生~都市と農山漁村の関係の再構築」
坂本誠・地方自治総合研究所常任研究員
14:45-17:15 分科会
①「有機農業・環境保全型農業と地域づくり」
助言者:関耕平・島根大学教授
司会:朝岡幸彦・白梅学園大学特任教授
②「元気な集落づくり~定住対策・集落再生」
助言者:井上果子・宮崎大学地域資源創成学部准教授
司会:水谷利亮・下関市立大学教授
③「学校を核とした地域づくり」
助言司会:田開寛太郎・都留文科大学准教授
*少し早めに終了し、木城学園内見学
④「町村長交流会」座長:平岡和久・立命館大学教授
17:45-19:30 夕食交流会
令和6年5月11日(土)
9:00-11:15 シンポジウム「ムラの未来を支える地域の誇り」
コーディネーター:平岡和久・立命館大学教授
シンポジスト①:黒木定藏・前西米良村長
シンポジスト②:半渡英俊・木城町長
シンポジスト③:川名俊和(木城町に移住された方)
シンポジスト④:小山大介・京都橘大学准教授
詳しくはコチラ➡''https://kagayaku-lg.org/event/240510/''
************
事務局便り
第4回理事会のご案内
日時 : 5月11日(土)午後1時30分
場所 : 茨城県総合福祉会館3階 多目的ホール
議題
第35回まちづくり学校について
組織拡大推進計画について
避難計画調査検討について
第5回理事会のご案内
日時 : 6月8日(土)午後1時30分
場所 : 茨城自治労連会館2階大会議室
議題
組織拡大推進計画について
避難計画調査検討について
第50回総会議案について
第50回茨城県自治体問題研究所総会
と き:2024年7月7日(土)午後1時30分から
ところ:茨城自治労連会館(つくば市花畑3-9-10)
電話:029-864-2548
今月の 川柳
うら金をのぞいてみたら紅麹
覇権主義おごる平家に想いはせ
子育てに甘言されて銭とられ
硝煙のにおいかついで海渡り
雲流れ人も流れて金流れ
見栄はってアンポ安保とお手を出し
行く春やスズメの涙ふいてやり
能登はるかガザへの想いさくらかな
老々とさくらトンネルくぐり抜け
円ドルの吹雪をのんで胃がもたれ
泉 明 羅
(泉明羅・本名 福田正雄 水戸市在住、句歴 四十二年、所属 元吉田川柳の会)
新刊紹介
地域居住 と まちづくり
多様性を尊重し 協同する地域社会を めざして
中 山 徹 編
A5判並製カバー、314頁 定価3,520円
日本の諸都市を初め、中国、イギリス、カナダ、そしてデンマーク、モンゴル、さまざまな場所で、住まうことの豊かさを求める市民の暮らしと活動を伝える。
「I 参加型まちづくり」 「Ⅱ 子育てしやすいまちづくり」 「Ⅲ 高齢者が暮らし続けられるまちづくり」
「Ⅳ 少数民族等の文化を生かしたまちづくり」 「V 人口減少と持続可能なまちづくり」の5つの柱から、地域での暮らしを重視した「まちづくり」のあり方を、興味尽きない図版、写真を多数駆使して考える。
目次よリ
はじめに一人口減少時代におけるまちづくりの基本方向一 / I 参加型まちづくり / Ⅱ 子育てしやすいま
ちづくり / Ⅲ 高齢者が暮らし続けられるまちづくり / Ⅳ 少数民族等の文化を生かしたまちづくり /
V 人口減少と持続可能なまちづくり / おわりに くこの時代に空間的最適解をどう求めるか)
私たちはどのような社会に暮らしているのか
基礎から考える社会保障
村田隆史・長友薫輝・曽我千春編
A5判並製カバー、310頁 定価2,970円
私たちは、どのような社会に暮らしているのか。生活を支える制度や仕組みを基礎から考える。 社会保障のあゆみ、制度、機能を基本理念に基づいて解説し、その現状を年金・医療・介護・労働保険、障害者福祉、子ども家庭福祉、公的扶助の各論から示す。併せて、アメリカ、韓国、ドイツ、イギリスの社会保障を概説し、社会保障が当面する課題を、財政、福祉労働、市場化・営利化・産業化の観点から明らかにする画期的なテキスト。
目次より
第1部 社会保障の発展過程と理念・概念 第1章 社会保障のあゆみと基本理念/第2章 社会保障の機能と体系/第3章 社会保障をめぐる論点 第2部 社会保障の制度各論 第4章 年金保険制度/第5章 医療保険/第6章 介護保険制度/第7章 労働保険[労災保険0雇用保険]/第8章 障害者福祉/第9章 子ども家庭福祉/第10章生活保護と低所得者施策 第3部 諸外国の社会保障 第11章 アメリカの社会保障/第12章 韓国の社会保障/第13章 ドイツの社会保障/第14章 イギリスの社会保障第4部 社会保障が当面する課題 第15章 社会保障と財政/第16章 社会保障と福祉労働/第17章 社会保障の市場化・営利化・産業化
■自治体研究社 〒162-3512新宿区矢来町123矢来ビル4F TEL:03-3235-5941/FAX:03‐3235‐5933
http://WWW.jichiken.jP/ E‐Mall info@jichiken.jp
------------------------------
主要ページのご案内
→月刊「いばらきの地域と自治」最新号をどうぞ;NEW!
先月以前のものはこちら→月刊「いばらきの地域と自治」既刊号すべて
過去のスクラップは→過去の自治関連ニューススクラップ
------------------------------
a:110134 t:13 y:23