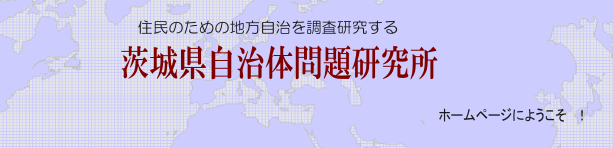茨城の自治ニュース
月間自治ニューススクラップ(茨城県内の出来事を中心に )
2024年06月
災害・対策(能登半島地震含む)
大洗の防潮堤 完成 今月末水門建設、区間4.3キロ (6.21 茨城)
東日本大震災を受け、県が津波対策の一環として進めてきた県内の防潮堤整備で、残っていた茨城港大洗港区(大洗町)の工事が今月末に完了する。2013年の整備開始から約10年を経て、太平洋沿岸を守る重要なインフラが整う。県は「安心安全の一助になる」とする一方で、避難や防災意識など市町村と連携したソフト対策にも力を入れる。
同港区の防潮堤区間は約4・3キロで、高さは4・5~7・5メートル。同町の市街地や水産ふ頭地区(大洗漁港)を守る形で整備された。13年4月から整備に着手し、20年度末に完了する予定だったが、計画の一部変更などにより3年ほど遅れが出ていた。
県は13年度から順次、防潮堤整備を進めてきた。海岸や河川、港湾、漁港の後背地など、住宅や幹線道路を控えた特に緊急性の高い箇所で新規建設やかさ上げを実施。総延長約53キロ。事業費600億円超で、主に震災復興に関わる国の交付金を活用した。
防潮堤は数十~百数十年に1度の頻度で発生が予想される最大4・2メートルの「レベル1(L1)」津波を想定。数百~千年に1度の頻度とされる最大14・8メートルの「レベル2(L2)」津波には、避難に軸を置いたソフト対策が求められる,県は12年8月、L2を想定した新たな津波浸水想定区域を公表した。沿岸10市町村はハザードマップ改定や津波避難タワー、避難の案内標識の整備、避難訓練などに注力。県も啓発イベントなど、ソフト事業に取り組んできた。防潮堤の完成に、同町漁協の臼庭明伸参事は「町も漁港も船も守られる理想の形になった」と歓迎。
防災部局の女性1割 「ゼロ」市区町村は57% 内閣府調査 (6.27 朝日)
全国の自治体の防災・危機管理部局における女性職員が1割余にとどまっていることが内閣府の調査で明らかになった。女性職員が少ないと、防災マニュアルにおける女性や高齢者、子どもへの配慮や、必要な物資の備蓄など防災対策にも影響が出ている実態も浮かび上がっている。
避難所運営・備蓄に影響
内閣府が47都道府県と20指定市及び1721市区町村に、昨年12月31日時点で調査した結果を26日発表した。調査によると、都道府県の防災・危機管理部局(本庁)に配置されている女性職員は平均12・3%(前年は11・1%)。最高は岩手県の22・5%、最低は島根県の0%だった。市区町村(本庁)で防災・危機管理部局に配置されている女性職員は平均11・5%(同9・9%)。防災・危機管理部局に女性職員がいない市区町村は57・4%(同61・l%)にのぼった。人口規模が小さい自治体ほど、女性職員の比率が低くなる傾向がみられた。
なぜ女性が少ないのか。 一般的に防災や危機管理を担う部署では24時間問わず緊急対応が多い。家庭で育児や介護といったケア労働を多く担っているのが女性であるため、配置しづらいとされている。
自治体が定める避難所運営のマニュアルに「プライバシーの確保」や「妊産婦、乳幼児を持つ女性への支援」を記載している割合は、女性職員比率が高い自治体ほど高まる傾向がみられた。「女性への暴力やセクハラ防止のための安全対策」は、人口10万人以上の自治体では7l・l%がマニュアルに記載しているのに対し、人口3万人未満の自治体では35・6%にとどまる。備蓄品への影響もみられた。女性職員がゼロの市区町村と10%以上の市区町村を比べると、ゼロの市区町村はオムツやミルク、介護食といった備蓄をしている割合が少なかった。
6月に決定された政府の「女性活躍◆男女共同参画の重点方針」(女性版骨太の方針)にも、防災現場で女性参画を進めることが盛り込まれている。
原発問題(東海第二原発関係も含む)
核燃料開発、点検不正、(6.14 朝日)
原発の核燃料の研究開発をする「日本核燃料開発」(大洗町)が放射性廃液タンクなどで10年以上必要な点検をせず、虚偽の記録を作っていた問題で、同社は13日、県庁で記者会見を開いた。原子力規制委員会から「会社全体の問題」と指摘されたことについて、同社の浜田昌彦社長は「決して個人だけに問題を押しつけてはいけない」と、会社側の責任を認めた。
同社によると、2009~22年度、保安規定で定められた放射性廃液タンク内側の点検や放射線管理区域の気圧を監視する警報計器などの点検をしていないのに、虚偽の記録を作成していた。不正発覚後に点検を実施し、設備の安全性は問題がなかったという。同社では21年にも同様の点検不正があったことが判明しており、当時点検を担当していた社員が今回問題となった設備の点検も担当していた。
同社は社員にかかる仕事量が多かったことを認めた。業務量を減らすために人員を増やし、別の社員に引き継ぎを進める中でヽ今回の不正が発覚したという。
東海第二原発防潮堤基礎に複数不備 規制庁「造り直し含め検討を」 (6.21 朝日)
調査の不十分さ指摘 原電、補修か建て直しか判断へ
日本原子力発電東海第二原発(東海村)の安全対策工事で、防潮堤の基礎部分に施工不備が見つかった問題をめぐり、原子力規制委員会の審査会合が18日に開かれた。原電は不備の「全容」を報告したが、原子力規制庁は「調査は不十分」として造り直しを含めて検討するよう求めた。
原電は、公式には9月の工事完了を目指しており、7月中旬ごろまでに補修工事か建て直しかを検討していくと応じた。昨年6月に発覚して工事を中断。10月に規制庁に報告し、施工不備を公表していた。
18日の会合で原電側は、音響探査などで調べた「不具合の全容」を報告した。それに対して規制庁側は、全容を把握するための調査が不十分だと指摘。音響探査には十分な信頼性がないとし、「直接確認できていないため科学的合理性が薄い」とし、「抜本的に設計を見直し、地中連続壁の造り直しを含めて検討してほしい」と述べた。
5月27日に現場を視察した東海村の山田修村長は「けっこう大変な不具合。どう考えても9月には終わらないと思った」と話していた。
「放射性物質拡散予測は過小評価」 東海第二差し止め控訴審原告側 (6.22 朝日)
日本原子力発電が再稼働を目指す東海第二原発(東海村)の周辺住民らが、原電に運転差し止めを求めた訴訟の控訴審の第3回口頭弁論が21日、東京高裁(谷口豊裁判長)であった。原告側は、県が要請し原電が試算した事故時の放射性物質の拡散予測について「最大17万人避難」は過小評価だ、などと主張した。
2021年3月にあった一審判決は原発の周辺30キロ圏内の自治体の避難計画が「整えられているというにはほど遠い」などとして、運転の差し止めを命じ、双方が控訴している。この日は原電側の口頭弁論はなかったものの、一審判決は「判断時期を見誤った極めて不合理なもの」と、控訴理由書などで主張している。
一方、原告側はこの日の弁論で、事故想定や被曝線量が過小評価されていると指摘する専門家の意見を紹介。
「誤った避難人口試算で避難計画の実効性は検証できない」と主張した。また防潮堤の基礎部分に施工不備が見つかった問題について、「内部告発がなければ公表せず隠蔽し続けた可能性がある」と訴え、原電には技術能力・品質管理能力が欠如していると主張した。
地方制度・自治体論・地方自治一般
地方自治法改定案の狙い (6.1 しんぶん赤旗)
龍谷大学教授(行政法)本多:滝夫さんに聞く。
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と国が判断すれば、地方自治体に対して行使できる新たな「指示権」(補充的指示権)を創設する地方自治法改定案。衆院で可決され、参院に送られた改定案の問題はどこか、その狙いは何か。今回の改定案では地方自治体に対する国の「指示権」が問題になっているが、国の関与の仕組みがどう変わるのか。
現行の地方自治法は第11章で、国の関与の基本的な原則と類型を定めています。245条第1号で助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行と、同条第2号で協議といった基本類型を定めています。同条第3号では基本類型に当てはまらない関与があるとも定めています。自治体の事務には法定受託事務と自治事務がありますが、3号の関与や、1号に規定している代執行は自治事務には使わないとしていますし、指示も例外です。法定受託事務には代執行を用いることができますが、第3号関与は例外です。
国の関与には地方自治法に基づくものと、災害対策基本法や感染症法などの個別法に基づくものがあります。個別法でも地方自治法が定めている関与の基本類型によるのが原則です。
ところが、今回の地方自治法改定では、第14章という新しい章を設け、そこに「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」という極めてあいまいな要件で、「特例関与」を創設します。自治体に意見の提出を求めること、「補充的な指示」、都道府県と市町村の事務処理の調整など、関与の基本類型にはない新しい関与をつくりだし、関与の仕組みを大きく変えているのです。
今回新たに創設される「補充的指示権」は個別法で間に合わないときに地方自治法に新設する特例関与を使いなさいというもので、原則と例外が逆転しています。そういう仕組み自体が、地方分権改革の考え方を根こそぎ否定していると思います。
パスポート発行3倍増 23年県内コロナ反動 (6.4 茨城)
2023年に県内市町村が発行した一般旅券(パスポート)の件数が5万8927件に上り、前年の3倍増と急回復したことが3日、県のまとめで分かった。コロナ禍で申請が落ち込んでいた反動で、5類移行後に急増したとみられる。
ただ、海外旅行者数の回復は遅れており、旅行業界は「今後の円安の状況次第」と動向を注視する。
「消滅可能性 自治体」を問う (6.8 日本農業)
4月に有識者らでつくる「人口戦略会議」が発表した消滅可能性自治体の波紋が広がる。同会議副議長で10年前も同様の推計で中心人物だった増田寛也氏(日本郵政社長)に狙いや推計に関する批判への受け止めと、農村政策を専門とする明治大学の小田切徳美教授に見解などを聞いた。
増田寛也氏「静かな有事」に警鐘
・大都市の問題可視化したい
・課題向き合い考える契機に
・世代交代勧め個性を生かして
小田切徳美氏 地域づくりふれずに
・危機感醸成の考え自体あやまり
・緩和と適応策バランス必要
・関係人口など多様な指示で
「女性減って自治体消滅」? (6.19 朝日)
「若年女性」人口を指標に、自治体が消滅する危機を訴えた人口戦略会議。メデイアや行政に注目された一方で、社会に漂うしらけ感、当惑――。課題は「自治体の消滅」なのか? 3人の意見を紹介。
山田由梨 作家・演出家・俳優 「産めない社会 政治の責任」
小熊英二 歴史社会学者 「『地域』を見据えた議論を」
岩本美砂子 女性学・政治学者 「人口政策 左右される身体」
小熊の指摘は興味深い。
「自治体は地域とイコールではない。明治21(1888)年には町村が7万以上あった。しかし明治・昭和・平成の大合併を経て、今の基礎自治体数は1741、国際的に見ても日本は自治体が少ない国です。一つの自治体には数十の集落がある計算になる。・・・今の過疎問題の焦点は周辺集落です。
例えば平均年齢が75歳を超えた山間集落にいつまで上下水道や道路の整備を続けるのか。住民を中心集落に集約するなら新住居や移転の費用をだれが負担するのか。移転で体調不良や認知症が増えたら、むしろ人権面でも経済面でもコストがたかくならないか。中心集落で若年女性が増えても、こうした周辺集落の課題解決には直結しません。
自治体を単位に地域を語るのは、そうした実態に即していません。」
移動難しい人向け つくば市が移動投票所 (6.20 朝日)
つくば市が、10月27日投開票の市長・市議選で、投票所への移動が難しい有権者を対象にした移動投票所の設置を計画している。
五十嵐立青市長は19日、市選挙管理委員会の指摘を踏まえ、今秋の選挙前に市内全域で実証実験をする意向を明らかにした。
市は郵便投票制度の対象となる要介護度5の高齢者や身体障害者などのほか、要介護度3、4の高齢者らを含め、期日前投票での実施を計画する。オンデマンド型で、ネットや電話で予約すると、投票箱を積んだ車が自宅近くまで来て、車内で投票できる仕組み。車は車いすでも乗降可能なタイプを使う。
通常の投票所と同じように、立会人も配置する。対象者は約5千人だが、市は過去の投票実績などから希望者は100人程度を見込んでいる。市は今年1月、市内の筑波、臼井2地区で実証実験を行った。その結果を踏まえて市内の一部で実施する構想だった。市議会や市選挙管理委員会から「公平性に欠ける」などと指摘があり、市は実施対象を市内全域に変更したが、3日、市選管から全域での実証実験を求められていた。
地方分権逆行 教訓置き去り、指示権「戦前体制」懸念の声も (6.20 朝日)
「地方分権への逆行」との懸念が払拭されないまま、改正地方自治法が19日成立した。国が「非常時」を判断し指示権を行使して地方を従わせるという法律。国が地方に「命令」し、総動員体制で戦争に突き進んだ日本の歴史がどこまで顧みられたのか。日本が戦争に突入すると、大正の「分権改革」から15年ほどで集権へと逆戻りする。
43(昭和18)年の改正で、首長選任に関する内務省の権限と、法律の根拠なしに国が自治体に事務の委任を「命令」する権限が復活。食糧増産や、徴兵に伴う遺族の社会保障制度など戦時に必要とされた事務を全国の自治体が担うようになった。
戦後、憲法は地方自治の本旨を明記。2000年の地方分権改革で機関委任事務が廃止。法律の根拠なしには国は地方に関与できなくなり、その関与も「必要最小限」とする原則が地方自治法に明記された。
政府は今回の改正を「個別法がカバーしきれない想定外の『法の穴』を埋めるための措置」(総務省幹部)と説明。しかし、国会審議では行使の要件である「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」を具体的に示さず、個別法改正で対応できるのではとの疑間は払拭されなかった。国の恣意的な判断による指示権の乱用の恐れがあるとして、野党側から「分権逆行」批判が噴出。日本の地方自治に、今回の新たな指示権はどんな影響があるのか。市川教授(同志社大学)は、地方分権改で確立した関与の原則に反する可能性があるとして、「行使の要件があいまいで、『取扱注意』だ。将来にわたって注視する必要がある」と指摘した。
改正規正法が成立 政治資金 透明性に懸念 (6.20 茨城)
派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた自民党提出の改正政治資金規正法は19日の参院本会議で可決、成立した。不透明な資金を代表する政策活動費は領収書10年後公開を検討すると盛り込んだものの、黒塗りの可能性は否定されないなど、裏金事件の再発防止や透明性確保の「抜け穴」に懸念が残る。
賛成は自民、公明両党のみで、立憲民主党など全野党が反対。日本維新の会も衆院の賛成から転換した。岸田文雄首相が期待する政治不信の解消につながるかどうかは見通せない。
改正規正法は①「いわゆる連座制」として政治資金収支報告書の「確認書」交付を議員に義務付け②パーティー購入者名の公開基準額を「5万円超」に引き下げ③政党が党幹部らに支出する政策活動費の使途項目別金額・年月を公開④国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出義務化1などを規定した。施行は原則2026年1月1日。パーティー券基準は27年1月とする。
一方、国会審議の中で政策決定への影響が指摘された企業・団体献金は禁止されず、政策活動費も温存される。領収書10年後公開は、規正法の時効5年と整合性が取れていないと問題視された。衆参両院によると法案の実質的な審議時間は衆参合計25時間50分だった。
まちづくり・都市計画
本県の出生率 最低1.22 婚姻は初の1万件割れ (6.6 茨城)
厚生労働省が5日発表した2023年の人口動態統計(概数)によると、本県の合計特殊出生率は1・22となり、過去最低を更新した。生まれた赤ちゃんの数(出生数)も同1007人減の1万4898人で最少。昨年の婚姻件数は前年比825件減の9338件で初めて1万件を割った。出生数や婚姻件数の減少傾向が止まらない中、県は「少子化対策を一層推進していきたい」としている。
今回の統計を踏まえ、県少子化対策課は「結婚支援をはじめとする少子化対策を一層推進していきたい」と強調。同センターのPRを促進し、会員数増とマッチング率の向上を目指す。同統計ではほかに、死亡数が前年比348人増の3万7604人。死亡数から出生数を引いた県人口の「自然減」は、1355人増の2万2706人となり、17年連続で減少幅が拡大した。
長く空き家放置 5年で36万戸増 周辺3.9兆円損失、手入れ不足 地価に影響 (6.16 日本経済)
長期間放置した空き家は、周辺の不動産価格を押し下げる。国全体の経済損失は2023年までの5年で3.9兆円に上るとの試算を民間団体がまとめた。周辺住宅の売却や賃貸も難航しかねず、取引の停滞でさらに空き家が増える悪循環の懸念もある。
売却や賃貸といった目的がなく居住世帯が長期不在の放置空き家は18年から23年の間に約36万戸増えて約385万戸となった。うち7割超が戸建てだった。
複数のエリアを検証したところ放置空きの周辺半径50m以内の地価は下落傾向にあった。庭木の繁茂や害虫・害獣の発生、治安悪化への不安から、入居希望者が減ることが要因とみられる。過去の空き家の立地傾向などから、23年までに増えた戸建ての放置空き家のうち約8割が影響を与えると推計した。地下下落による損失は23年までの5年間で約3.9兆円に上ると計算した。
今回の試算に含まれないマンションの放置空き家の場合、所有者が不明になる方として管理費や修繕積立金の支払いが滞ることがある。マンション全体の資産価値が落ちる原因となる。
日本では人口が減っても一人暮らしの増加などで世帯数の拡大が続く。国立社会保障人口問題研究所の推計では世帯数も30年にピークを迎える。住宅の総需要が本格的に減り始め、空き家が急速に増えかねない。国は対策を強化しており、相続登記を義務化する法改正などを重ねてきた。都市計画や地域づくりといった広い観点から抜本的な対応を考える時期に来ている。
潮来IC‐波崎間 新道路 工業地帯、東関道直結 (6.24 茨城)
東関東自動車道と鹿島臨海工業地帯とをつなぐ新道路「鹿行南部道路(仮称)」が建設されることが23日までに分かった。起終点は潮来インターチェンジ(IC)と波崎地区工業団地周辺となる見込み。高速道路と直結することで交通アクセスが向上し、物流機能の強化や渋滞緩和などが期待される。国や関係自治体などによる検討委員会で24日に正式決定する。
関係者によると、新道路は東関道水戸線潮来ICと波崎地区工業団地周辺まで全長20キロ前後となる見込み。検討委で決定後、概略ルートや構造の協議、関係自治体の都市計画策定などを経て、新規事業化する。
開通時期は未定。県などは2014年2月から鹿行南部の交通課題を検討してきた。22年1月に県と鹿嶋、潮来、神栖の3市や東日本高速道路、国土交通省関東地方整備局で構成する鹿行南部道路(同)検討委員会を設立。継続して議論を続けてきた。
新たな道路により、太平洋側唯一の洋上風力発電設備の基地港湾として、鹿島港周辺への関連企業の立地促進を見込む。鹿島港と潮来ICの間には津波浸水想定区域があり、港からの緊急輸送ルートの確保にもつなげる計画だ。
地域経済
減りゆく街の書店 ネットに押され雑誌販売打撃 (6.2 毎日)
街の書店の減少が止まりません。全国の自治体のうち4分の1以上が書店が一店舗もない「書店ゼロ」に陥っています。こうした状況から経済産業省が3月、プロジェクトチーム(PT)を設置し、街の書店振興に乗り出した。
全国の書店の総店舗数は2024年3月時点で10,918店。10年前に比べて約4700店減っています。また、出版文化産業振興財団の調べでは、書店ゼロの自治体は3月時点で482市町村で全体の27.7%になります。
なぜ減っているのか。理由の1つは、街の書店を支えてきた本や雑誌の売り上げの減少です。特に雑誌が落ち込み、最盛期の1997年の推定販売金額1兆5644億円から22年は4795憶円に減っています。要因は、インターネットの発達で情報がより迅速かつ手軽に得られるようになったことなどが考えられます。アマゾンなどのネット書店での販売増加も影響を与えているとみられます。
紙の出版物の市場は縮小している一方で、電子出版市場は右肩上がりです。電子出版の市場規模は14年に1144億円でしたが23年には5351億円に拡大。電子コミックが中心で、電子出版市場の約9割を占めています。
本の売り方も多様化しています。例えば個人や法人が書店の本棚を借りて本を売る「シェア型書房」は各地に広がり、他にもセルフで本を買う「無人書店」が登場。コンビニ大手ローソンは書店併設型の店舗を全国に展開しています。経産省は3月、街の書店併設型の店舗を全国に展開しています。
今後については既存の中小企業支援策やコンテンツ振興策の活用を検討しています。偶然手にした本が一生の宝物になることがあります。そうした出会いの機会が失われないよう官民それぞれの立場で書店を守る取り組みをしていくべきだと思います。
外国人雇用企業28% 民間の県内調査製造業50%超す (6.2 朝日)
県内で外国人を雇用している企業は28・4%で、全国平均の23・7%を上回り全国8位とする調査結果を、帝国データバンク水戸支店がまとめた。「今後採用を増やす」(10・l%)と「今後採用を開始する」(13・5%)を合わせた外国人の雇用を拡大する意向の企業は23・6%だった。
調査は2月に県内の455社を対象に実施し、208社から回答があった。外国人を雇用している企業は業界別でみると、製造が52・9%と最も多く、サービスが25・0%、小売り23・5%と続いた。外国人の雇用・採用における課題としては、「スキルや語学などの教育」が56・3%と最も多く、「コミュニケーション」が5l・4%、「継続性・定着」43・l%と続いた。
厚生労働省によると、2023年10月時点の全国の外国人労働者数は200万人以上、雇用事業所数は30万力所以上で、いずれも過去最多。県内も同様の傾向で、茨城労働局によると、同年10月時点で5万4875人と過去最多。前年同期比で13・4%増えた。
地域づくり協 全国で100組織 農業が最多89組織 (6.4 日本農業)
(移住者派遣×人手不足解消)
移住者を職員として雇用し、組合員である各事業者に派遣する特定地域づくり事業協同組合の設立が全国で100にわたったことが総務省の調査で分かった。
派遣先の業種は農業が最多で89、JAが参画する組合もある。制度開始から5年目を迎え、地方の人手不足解消と移住促進に向けた新たな取り組みとして設立が広がる。
総務省によると、6月時点で103市町村に100組合が設立された。農業の他、豆腐店、介護、JA、高齢者宅の草刈りなどさまざまな派遣先があり、幅広く活動している。
農産物・加工品の輸出最高 本県42億円 コメ、菓子がけん引 (6.5 茨城)
本県の青果物、コメ、畜産物を合わせた農産物と加工食品の2023年度輸出額は前年度比41%増の42億3500万円で、過去最高を更新した。県が4日、発表した。農産物ではコメが83%増と大幅に拡大。加工食品は菓子類が2倍増となり全体をけん引した。県は事業者への支援強化と新規参入を促し、一層の販路拡大を目指す。
県が支援した事業者などへの聞き取りにより、農産物、加工食品の輸出額を調べた。輸出額の内訳は、農産物が前年度比33%増の17億5310万円、加工食品が48%増の24億82OO万円で、いずれも過去最高を更新した。
農産物は集計を始めた翌年の16年度から8年連続、加工食品は21年度から3年連続の更新。農産物で輸出額が最も多かったのは、コメの7億1千万円。特にシンガポール向けが3倍増、米国向けが2倍増と目立った。
県は人口減少による国内市場の縮小を見据え、県産品の輸出拡大に取り組む。農産物は常陸牛、コメ、サツマイモを「輸出の主要3品目」と位置付け、生産者と輸出先とのマッチングなどで支援。加工食品は高価格で販売が見込めるアラブ首長国連邦(UAE)など5力国・地域で、専門家による需要を調査するなど販路開拓に乗り出している。
県農産物販売課と県加工食品販売チームは「引き続き輸出に意欲のある事業者を側面から応援していく。輸出に取り組む事業者を増やし、農産品と加工食品の輸出額を拡大させたい」と意欲を示した。
「育成就労」法が成立 入管法改正 技能実習廃止 (6.15 茨城)
技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設する改正入管難民法などが14日、参院本会議で自民、公明、日本維新の会、国民民主各党などの賛成多数により可決、成立した。公布後3年以内の施行で、2027年にも新制度が始まる。労働力不足解消のため、人材確保を目的に明記。「国際貢献」を掲げ、1993年から続く技能実習は廃止となり、政策の転換を迎える。政府は有識者会議を設置し、制度の運用について検討する。
育成就労は未熟練の労働者を受け入れて、即戦力とされる「特定技能1号」の水準に原則3年で育てる。熟練した技能を要する「特定技能2号」に移行した後は、事実上永住も可能。受け入れるのは農業、建設など16分野で、特定技能と対象をそろえて一体運用し、長期就労を促す。
技能実習で受け入れ仲介を担う監理団体は「監理支援機関」とし、外部監査人の設置を義務付ける。納税などを故意に怠った場合は永住許可を取り消し、別の在留資格に切り替える規定も設けた。
外国人に身分証として交付される在留力ードと、マイナンバーカードを一体化した「特定在留力ード」を先行する新制度も創設された。県内実習生1万7400人。
みどり法認定農家 1.5万人 (6.16 日本農業)
都道府県の認定を受けて化学肥料・農薬の使用を減らすなど環境負荷低減に取り組む農業者が5月時点で15,000人を超えた。「みどりの食料システム法(みどり法)に基づく認定者で、環境に配慮した生産を実践する農家らを都道府県が認定し、税制・融資で支援する仕組みだ。
5月末時点の認定者は、東京都を除く46都道府県の15,690人、4月の約5000人から大幅に増えた。福井県が9691人で最も多く愛媛県、和歌山県が続いた。(茨城県は、235人で11位)
茨城 工場立地全国トップ 昨年75件 3年ぶり返り咲き (6.19 日本経済)
経産省がまとめた2023年の工場立地動向調査によると、茨城県への企業による工場や研究所の立地件数が75件と22年を15件上回り都道府県で最も多かった。 22年は2位で3年ぶりに首位に返り咲いた。
立地件数は、製造業などが工場や研究所を建設するために1000㎡以上の用地を確保した件数を示す。北関東3県は多くの企業が本拠を構える東京圏と近く行き来しやすい。東京圏は国内最大の消費市場、23年も製造関連の拠点を設ける動きが活溌だった。広い用地を東京圏よりは割安に取得できることで北関東での工場立地を促している。
茨城の工場立地件数は21年、22年と愛知県に譲った都道府県トップを23年は奪回した。立地面積も165haと22年の116haを4割上回ったが、全国順位は北海道に及ばず2位だった。
県内を地域別にみると物流面で利便が高い。圏央道沿線の県南部、県西部地域の立地が引き続き多かった。
ベンチャー、随意契約容易に 県が新制度、まず9社認定 (6.22 朝日)
県内に拠点のあるベンチャー企業が、県と随意契約を結びやすくする事業者認定制度が21日、スタートした。実績がないために取引に苦戦するベンチャー企業を後押しする狙い。県は第1弾として9社を認定し、発表した。今回認定されたのは、健康や福社のほか、防災や土木分野で活用が期待される商品やサービス。
制度の対象は県内に本社や事業所がある企業。創業年数に制限は設けていない。新規性や独創性、社会的有用性などを大学教授らが審査する。
今後、随意契約に向けて県庁内で各課が担当する事業とのマッチングを進める。
有機農業推進へ始動 石岡市・かすみがうら市・笠間市 (6.23 茨城)
石岡、かすみがうら、笠間の3市が、生産から消費まで地域ぐるみで有機農業を推進するモデル地区を目指して動き出した。本年度中に「オーガニックビレッジ宣言」を行いたい考え。3市はそれぞれ検討会を開き、具体的な実施計画の策定に向けて始動。学校給食への提供を検討するなど、有機農業の普及拡大を狙う。
年度内「宣言」目指す
農林水産省によると、同宣言をしているのは2023年度現在、全国で93市町村。農業者などによる検討会の開催や試行的な取り組みを経て、5年間の有機農業実践計画を策定する。その上で、国からの承認を得て宣言する流れだ。昨年、本県で初めて常陸大宮市が宣言した。
同宣言は農水省が全国のモデル地区に対して支援する取り組み。「みどりの食料システム戦略推進交付金」により、栽培技術の実証や販路拡大など、有機農業の拡大に向けた事業を支援する。同省は25年までに全国で100市町村、30年までに200市町村の宣言を目標に掲げる。
物流やバスDX化支援 機器導入 県が上限200万円 (6.29 茨城)
貨物運送や乗り合いバス事業者を対象に、県はデジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した業務効率化を支援する。物流停滞などが懸念されている「2024年問題」の解消が狙い。新システムを導入する事業者に、200万円を上限に費用の半額を補助する。事業者の申請を受け付ける。
県中小企業課によると、補助の対象とするのは、効率化を目的とした新たなステムや機器の導入にかかる経費。予算額は貨物運送、乗り合いバスを合わせて総額5千万円。1事業者当たり200万円を上限に、費用の2分のーを補助する。
導入後の効果を把握し、業務改善に関わる周知活動にも生かす方針。
県内に事業所がある中小貨物運送事業者や中小倉庫事業者が対象となる。貨物運送事業者は、取引適正化に努める「パートナーシップ構築宣言」を行うことが条件となり、県は約15事業者を見込む。乗り合いバス事業者は、県内に営業所のある10事業者への補助がすでに決まっている。
環境と開発 災 害
偕楽園 ホタル再生へ 県、新たな誘客策に (6.14 茨城)
日本三名園に数えられる偕楽園(水戸市)で、県がホタルの生息域の再生に乗り出した。民間の環境団体と連携し、月池周辺の湿地帯に水路や池、あぜなどを整備。成虫や卵を放つことで、ホタルが飛び交う環境づくりを進める。夏の新たな魅力として、偕楽園周辺の誘客につなげていく方針。
整備を進めているのは、偕楽園拡張部の月池南東部に位置する「蛍谷」と呼ばれる湿地帯。2~5月にゲンジボタルの生息や産卵に必要な水路、あぜ、岩ゴケのほか、ヘイケボタルが生息する池などの環境を段階的に整備した。
月池南側に隣接する湿地帯でも、ヘイケボタルが生息できる環境にするため、土入れや水性植物の植栽などを行った。周辺の園路灯や樹木の電飾も配慮し、6月から7月上旬にかけて、消灯や減灯も実施する。
医療・福祉・社会保障・教育
県公立校教員志願してほしいが 人材難 試験前倒しでも倍率最低 (6.6 朝日)
2025年度に採用する県公立学校の教員選考試験の1次試験が5月に実施された。教員の志願者が減少するなか、優秀な人材の確保を目的に例年より約1カ月半前倒ししたものの、志願者数は前年度より600人以上減った。県教育委員会によると、1次試験は5月12日に実施。民間企業の採用活動が早期化していることに対応するため、試験日程を前年度の6月25日から大幅に早めた。しかし、全体の志願者数は2911人にとどまり、前年度より647人減少した。
小中高校と特別支援学校の志願者を合わせた「教諭」の志願倍率は2・71倍で、過去最低となった。志願者数を受験会場別でみると、首都圏の学生らを対象にした東京会場が655人で、前年度の1121人から大幅に落ち込んだ。
優秀な教員確保が喫緊の課題となるなか、県教委が今年2月に打ち出した施策「いばらき教員養成プロジェクト」で、教員を志望する中高生をターゲットにした活動に力を入れる。現役教員との研修会「いばらき輝く教師塾」の参加対象を拡大し、
今年度から高校生も参加できるようにした。ほかにも、小中高校や特別支援学校での大学生のインターンシップの受け入れ促進や、県内での教員志望者に向けた専門の大学入試枠「地域教員希望枠」
の設置などに向けて調整を進めている。
給食無償化 6年で7倍 文科省が自治体調査 (6.13 日本農業)
文部科学省は小中学校の給食を無償化した自治体の目的や成果、課題を探る初の実態調査結果を発表した。全児童生徒に完全無償化した自治体が全体の3割と6年間で7倍に増え、多子世帯などに限る一部無償化を含めると4割だった。
一方、都道府県間の給食費(食材費)は1.4倍の開きがあることも判明。“1食の格差“は一律無償化を検討する際の大きな焦点になりそうだ。
調査は、政府の「こども未来戦略方針」に基づき、国による給食無償化の課題を整理する狙い。都道府県・市区町村の1794教育委員会・事務組合に1年かけて尋ねる。
昨年9月時点で無償化を「実施中」の自治体は722あり、「実施予定」が40、「過去に実施していた」は13。実施中のうち全ての児童生徒を対象とする完全無償化が全体の30%に当たる547で、残る175は多子世帯や小学生のみ対象の一部無償化だった。
無償化の目的は「子育て支援」が90%を占めた。成果は児童生徒が「家庭環境に関係ない食育の充実」保護者は「安心して子育てできる環境の享受」教職員は「給食費の徴収負担の解消」が最も多かった。課題は「予算の確保」が18%と最多で、「食育意識の低下」も4%あつた。
同日、学校給食実施状況調査結果も公表。完全給食は公立小99.5%、公立中97.1%と過去最高に。1か月の給食費は、小学校3933~5314円、中学校4493~6282円と都道府県間で1.4倍近い格差があった。
小中給食無償化実施3割 自治体6年で7倍子育て支援目的 (6.13 朝日)
公立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化している自治体が、2023年9月時点で、全国の3割にあたる547あつたことが文部科学省の調査で分かった。17年度の同様の調査から6年で約7倍に増え、子育て支援の一環で無償化する動きが広がっている状況が浮かんだ。政府は今後、全国で無償化できるか検討を進めるが、費用面などから実現するかは不透明だ。
全国拡大は財源の壁
文科省が12日、全国の自治体の給食費無償化の状況を調べた結果を公表した。児童生徒全員を対象にするか、支援要件を設けるなど一部の児童生徒を対象にして「無償化を実施中」としたのは722自治体。約150自治体が多子世帯に限定するなど支援要件を設けていた。一部の学年に限定して無償化しているところもあった。調査時には無償化していなかったが23年度中に実施予定とした自治体も40あった。
無償化した理由についても複数回答可で聞いた。652自治体(90・3%)が「保護者の経済的負担の軽減、子育て支援」、66自治体(9・l%)が「少子化対策」(子どもの増加を期待した支援)、37自治体(5・1%)が「定住・転入の促進、地域創生」(人口増を期待した支援)を選んだ。
一方、無償化の継続が難しい面も見えた。722自治体のうち24年度以降に続ける予定はないと答えた自治体は82(11・4%)あった。文科省の担当者によると、財源の問題から、時期を限って無償化する自治体は、珍しくないという。
中学生「通学路の危険 改善を」 常澄中生徒の陳情 水戸市議会採択 (6.19 朝日)
水戸市立常澄中学校の生徒たちが、自分たちの通学路にひそむ危険な場所の改善を求める陳情書を水戸市議会に提出した。市議会は6月定例会の閉会日である18日、全会一致で採択した。
この陳情の始まりは授業の一環で、生徒一人ひとりが通学路に危険な場所がないか探したことだった。常澄中学校は、水戸駅から8キロほど南東で、大洗町との境に位置する。生徒の約9割が自転車通学。5キロ以上の距離を通学する生徒もいる。昨年、当時の2年生が危険な場所をたくさん見つけ、整理していった。
自分たちで気をつけていても、私たちにはどうにもできないことがある。自転車のライトでは前が見えづらいほど暗くなる場所に、明かりを。車が止まらない十字路に横断歩道か信号機を。消えかけている自線を引き直してほしい――。
今年1月、生徒3人を代表として、通学路の安全確保を求める陳情を市議会に提出した。信号機や横断歩道のない交差点、消えかかった白線、照明がつかなくなったトンネル、カーブミラーのない坂道。この四つの改善を求めた。市議会は陳情を受理し、教育分野を所管する「文教福祉委員会」で話し合った。委員は現地を視察して危険性を確認した。
市は、自線の引き直しやトンネル照明の付け替えについては今年度中にも対応する方針だ。また、通学路の危険について各校に調査を頼む通知文に「児童生徒の意見の反映に努めるよう」にと記した。
「恵」6施設、714万円過大.徴収 事業者指定取り消し県内8施設に連座制 (6.27 朝日)
障害者グループホーム(GH)運営大手「恵」(本社・東京都)の愛知県内にあるGHが食材費を過大徴収していたとして、県と名古屋市が事業者指定の取り消しを発表したことを受け、厚生労働省は26日、同社が茨城を含む全国に展開するGHに対し、事業者指定の更新を認めない「連座制」の適用を決めた。
また、茨城県内のGHでも食材費を過大徴収していたことが同日、明らかになった。
県によると、同社が運営する県内のGHは、7市に8施設ある。定員は1施設あたり10~20人。最大で計120人が入所可能という。厚労省の調査によると、このうち6施設で116人から計約714万円の食材費の過大徴収があった。障害者総合支援法は、指定取り消しの理由となった不正行為に法人の組織的な関与が認められれば、連座制を適用すると定めている。行政からの給付が受けられないため、事実上運営ができなくなる可能性がある。 ′
厚労省は連座制の適用と同時に、同社のGHがある県などに対し、入所者の退去や転居を支援するよう協力を求めた。県内には、今年4月時点でGHが362施設あるといい、県の担当者は「別の施設へ移ることを希望する入所者については、支援をしていく」と話した。