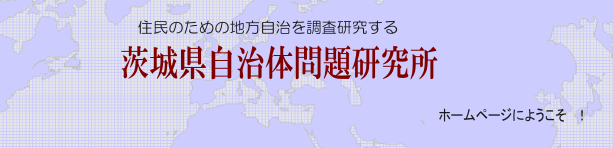FrontPage
2024・07・22更新


山田祇園祭=行方市
神輿が暴れれば暴れるほど縁起がいいとされる。「暴れ神輿」は迫力満点 山田祇園祭り7月27・28日、18時頃から・八坂神社(行方市山田) この祭りは300年以上の歴史があり、市指定民俗文化財となっています。また山車の曳き回しも行われ、若蓮と呼ばれる若者達が汗だくになりながら勇壮な山車と共に、夜遅くまで街を練り歩きます。
「女性減って自治体消滅 」論の再考
「若年女性」人口を指標に、自治体が消滅する危機を訴えた人口戦略会議。
6月19日付朝日新聞~耕論~が「女性減って自治体消滅 ?」 と題して3人の意見を紹介。山田由梨(作家・演出家・俳優)「産めない社会 政治の責任」、小熊英二(歴史社会学者)「『地域』を見据えた議論を」、岩本美砂子(女性学・政治学者 「人口政策 左右される身体」。いずれも興味深い論稿です。とくに、小熊英二氏の指摘は深い示唆を与える。
氏の意見を要約してみよう。
「自治体は地域とイコールではない。明治21(1888)年には町村が7万以上あった。しかし明治・昭和・平成の大合併を経て、今の基礎自治体数は1741、国際的に見ても日本は自治体が少ない国です。一つの自治体には数十の集落がある計算になる。
今の過疎問題の焦点は周辺集落です。例えば平均年齢が75歳を超えた山間集落にいつまで上下水道や道路の整備を続けるのか。住民を中心集落に集約するなら新住居や移転の費用をだれが負担するのか。移転で体調不良や認知症が増えたら、むしろ人権面でも経済面でもコストがたかくならないか。中心集落で若年女性が増えても、こうした周辺集落の課題解決には直結しません。自治体を単位に地域を語るのは、そうした実態に即していません。」
自治体消滅ではなく、地域・周辺集落の自滅こそが焦点であり、施策の眼目ではないか との指摘は重要である。
今月の俳句
花鳥の影時々過ぎる窓暑し
滴(したた)りのひかり一筋筑波石
膝痛を堪えし日々や栗の花
廃屋に歳月ながれ流れ合歓の花
鎌の銹(さび)砥石に流し走り梅雨
高 島 つよし
本名 高島剛 常総市在住、句歴七十年 元茨城県職員 元小貝保育園長、当研究所顧問
寄 稿
開発優先、福祉切りすての「水戸市第7次総合計画」
~抜本的な見直しを求める
田中 真己(水戸市議会議員)
水戸市の行政運営の基本方針、最上位計画である「水戸市第7次総合計画」が2024年3月議会で議決されました。計画期間は今後10年間(2024年度から2033年度まで)であり、水戸市の目指す将来都市像を「こども育む くらし楽しむ みらいに躍動する 魁のまち・水戸」と定めています。
市街地再開発やマンション建設に多額の税金を投入
第一に、「活力あるみと」における「都市核」の「都市機能の充実」の名目で、市街地再開発やマンション建設に多額の税金を投入する計画となっています。
「みと未来財政プラン」では「4大プロジェクトにかかる市債残高の償還にともない、公債費負担の大幅な増加が見込まれる」としながら、今後も再開発や特定業者優遇のマンション建設に多額の税金を投入する計画です。
水戸駅前三の丸地区再開発では事業費100億に対して補助39億円(今年度になって7億円増額が決まり46億円)も投じてゼネコンとマンション業者を支援します。
優良建築物整備では泉町1丁目広小路の穴吹マンションに5.3億円、南町3丁目北地区の旧プリンスビル周辺に7.3億円が決定。3事業で約59億円の補助です。
さらに、泉町2丁目北地区の伊勢甚中央ビル、南町3丁目南地区の住友不動産が所有する旧ユニー跡地周辺も「新たな再開発の検討」が計画に明記されました。
5つの事業がいずれもマンション、テナントなどの計画で、いずれも大手ゼネコンやマンション業者を優遇する事業ばかりです。
いまも水戸駅南口を中心に、大型民間マンション建設が相次ぐなか、泉町・南町の至近距離、徒歩5分、350m以内に4カ所のマンション開発に税金を投入するなどありえません。財政負担も大きく他の事業を圧迫することは明らかです。
市長の言う「選択と集中」の間違いであり税金投入の中止を求めました。
真に市民が求める事業の目標・予算の拡充こそ
第二に、真に市民が求める事業を優先して計画を引き上げ、目標、予算を拡充することを求めました。中学生に続き小学生の給食費完全無料化や保育料の無料化をはじめとする子育て支援策の速やかな実行、築40年超えが過半数の老朽化した小中学校や市民センター、市営住宅の整備を早期に行うことです。
また、200か所近い被害の残る雨水対策、生活道路や通学路の整備など、市民が拡充を求める事業の目標・予算が不十分であり、計画の引き上げを求めました。
市が実施した「市民1万人アンケート」の声を素直に実行しようとすれば、開発よりも子育てや医療・福祉・教育を優先した市政を市民が求めていることが明らかだと主張し、市政の転換を求めました。
市民につめたい行革プラン~負担増や民間委託、福祉切り捨てメニューがずらり
第三に、行財政改革の断行の名による市民負担増や民間委託、職員削減に反対しました。これまでの行革プランでは「受益者負担の適正化」による公共料金値上げ、民間委託による図書館や放課後学級など身近な事業の民間委託、職員削減が行われてきました。
7水総計画が決定した後、6月に発表された「水戸市行政経営改革プラン」は、下水道料金やごみ袋料金・国保税などの更なる値上げの検討、「福祉施設のあり方検討」の名による高齢者・障害者施設の廃止や民間委託、市立幼稚園に続き保育園も民間委託の検討、民間委託拡大による職員削減など、これまでの行革プランを上回る福祉切り捨て、市民負担増のメニューが並んだものです。
日本共産党市議団は、低賃金への置き換えや待遇悪化をもたらす民間委託ではなく、職員増員で公的責任をはたし、市立保育園や福祉施設の拡充で公的責任を果たすよう求めました。再開発に巨額の補助をする一方、税や公共料金値上げで市民負担をふやすのではなく引き下げをするべきと主張しました。
ありえない合併と政令指定都市
第四に、広域合併の推進に反対しました。政令指定都市をめざす広域合併には、機運がない、現実性がない、財政支援もない状態です。合併特例債も今年度で終了、仮に水戸市が隣接自治体と合併しても61万人弱で基準の70万人にはなりません。
何よりも市民が合併を求めておらず(1万人アンケートでは意向調査さえしていない)広大な市域となれば、住民からは行政が遠い存在となり、行政サービス低下を招くものです。コンパクトシティを目指すと言いう7水総に広域合併もめざすと明記するのは大きな矛盾であり、削除すべきと主張しました。
市民の声で市政を動かす
以上のように、問題山積の「第7次総合計画」が決定してしまいました。しかし、これらを実行すればするほど市民の願いとの矛盾が広がることは避けられません。
毎日の暮らしの中で出される切実な要望は市長も議会も無視することはできません。
今後、要求にもとづく様々な市民運動を広げ、議会で取り上げることで、ひとつひとつ願いを実現するとりくみが大事になると思います。
真に市民の願いに応える水戸市政に変えるため、力をあわせて奮闘する決意です。
以上
(2024年7月12日脱稿)
************
今月の 川柳
へそくりも物価に追われ底をつき
パリパリと燃える聖火は今どこに
首都決戦終わってみれば元の鞘
旧札にしがみついてる老いのシワ
人権をかざして人権ふみにじり
軍拡に心乱れてクビがとび
産みたいが先だつものに見はなされ
大戦の予感でしょうか鳴くカラス
さよならと自民見送る夏の風
金欠に熱中症というパンチ
泉 明 羅
(泉明羅・本名 福田正雄 水戸市在住、句歴 四十二年、所属 元吉田川柳の会)
イベント案内

事務局通信
第50回茨城県自治体問題研究所総会 報告
7月7(日)、茨城自治労連会館において、第50回総会が開催され、その前段では、記念講演が行われた。記念講演及び第50回総会の内容は、以下のとおりです。
★記念講演
最初に、「自治体問題研究所の現状と課題 地方自治をめぐる情勢の特徴と自治体問題研究所の役割を踏まえて」と題して、自治体問題研究所(全国研)吉川 貴夫 事務局長が記念講演を行った。
講演は、地方自治と公務公共サービスを取り巻く情勢の特徴とこれを踏まえて、全国・地域の自治体問題研究所の役割、全国研の財政問題の経過・到達点・今後の方向について、報告が行われた。
国会において、改正地方自治法が可決・成立し、地方自治と公務・公共サービスの危機的状況のもとで、次々と出現する様々な課題に対して、問題点とあるべき方向を明らかにして、それを地域のなかで共有を図り、運動に寄与する自治体問題研究所・地域研究所の役割が拡大している。
情勢を踏まえて調査研究を行い、雑誌「住民と自治」等で情報を発信することや自治体学校・地方議員研修等を通して、学習交流を深める活動と意義はますます増している。
地域研究所の皆さんとともに、研究所の維持・発展を目指して奮闘して行くので、協力をよろしくお願いします。
★田中理事長あいさつ
ロシアのウクライナ侵攻が止まない。イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への無差別のジェノサイド攻撃が続いている。一刻も早い停戦・平和が求められている。
国内では、岸田政権による戦争国家体制づくりの暴走が続いている。地方自治法の改正は、憲法に保障された地方自治を踏みにじるもので、戦時体制に向けて自治体の動員を構築していく動きに対して、反対の声を強く上げて行く必要がある。
県内では、大型公共事業を優先して、県民生活を軽視する県政が続いている。
東海第二原発の防潮堤基礎工事部分の不備が明らかとなり、9月再稼働は厳しい状況にあるが、再稼働中止、廃炉を求める運動をさらに強めて行く必要がある。
こうしたなかで、住民運動、自治体労働運動に寄与する研究所の役割が、非常に重大になっている。1975年に茨城研究所は創立され、来年50周年の節目を迎えるが、学習交流・調査研究・組織強化のそれぞれの面で追及して、民主的地方自治の発展のため、積極的に貢献して参りたい。本年もよろしく、ご支援・ご協力をお願いします。
★来賓あいさつ(茨城自治労連 濱野執行委員長)
3月2日に、まちづくり学校が結城市民文化センター「アクロス」で開催され、研究所の皆さんに力強いバックアップをいただいて、成功裡に終わった。私たち自治労連運動の力にもなったと思っている。引き続き、次回の開催に向けて、いっしょに協力して進めたい。
研究所の会員拡大では、先月役員の1人が会員になったが、役員のなかでも会員が少ないので、これから会員の拡大に向けて、引き続きがんばっていきたい。
私たち自治体職場では、今、退職者が相次いでいるが、こうした自治研活動を通して、自分たちの仕事に、魅力とやりがいを発見できるような活動を続けて行きたい。引き続き、よろしくお願いします。
★2023年度活動経過報告・一般会計決算報告・特別会計決算・会計監査報告
2023年度 活動経過・決算・会計監査の報告では、叶谷事務局長・岡村事務局次長から報告され、すべて承認された。
【発言等】
・2023年度一般会計決算書、収入の部、繰越金で2023年度決算額が2024年度予算額より多いことについて説明を求められた。
資料を確認したうえで、後日、回答する旨の答弁を行った。
★2024年活動方針案・一般会計予算案・特別会計予算案について
2024年度 活動方針・予算では、叶谷事務局長、岡村事務局次長から提案され、全員で承認されました。
【発言等】
・2024年度一般会計予算書(案)のなかで、収入(会費)が2023年度と比べ減っているのに、支出において、全国研への納入額が大幅に増えているのはどうしてか。
2023年度決算額が増えているのは、過年度分会費の整理を行った結果、多額の会費納入があった。2024予算額では、全国研への納入が特段増えるという見込みではない。詳細は、資料等を確認したうえで、次回理事会で報告する。
・2024年度一般会計予算書(案)の全国研納入の摘要欄については、(丸めた数字ではなく)単価×登録人数で掲載すべきである。
・2024年度一般会計予算書(案)の2024予算額は提案のとおり決定し、摘要部分の積算根拠を修正することで了承を得る。
【2024年度 役員】
理事長 田中重博
副理事長 濱野 真・飯田三年・榊原 徹
理 事 池羽路一・石橋英司・佐川泰弘・佐藤英一・白石勝 巳・高畑 孝・長山重道
濱野 真・穂積建三・本田精一・山本千秋・渡邊久人・海﨑 章・酒井 進 歌川 学
監 事 岩瀬 亮・加藤木正
事務局長 叶谷 正
事務次局長 岡村瑞比古
顧 問 浅野長増・木戸田四郎・高島 剛・田村武夫・本田忠弘 宇佐神忠捷・恵田三郎・山浦五十一・宮田哲雄・川並英二
以上 文責 事務局長 叶谷 正
❉✼❅❄ ✽✾❀❃✻ ❊❉✼❅❄ ✽✾❀❃✻❊❉✼❅❄
新刊紹介
「補充的指示権」と地方自治の未来
●地方自治法「改正」が、集権化と行政民間化を加速する!
定価2,530円(税込み)
編著者:榊原秀訓 著 者:岡田知弘・自藤博行・松田亮三・本多滝夫・平岡和久・河合克義
感染症での混乱や災害等を名目にして、「改正」地方自治法には自治体に対する国の強い指示権(補充的指示権=特権的関与)が盛り込まれた。また、情報システムの「最適化」が求められ、自治体に代わってサービス提供を行う「指定地域共同活動団体」制度が創設された。本書では、国の国家安全保障政策やデジタル行財政改革などを背景にした集権化と、行政の公共性を放棄する行政民間化が加速化されている地方自治の現状を分析し、それらに対抗する地方自治のあり方を問う。
第Ⅰ部 地方自治の現在
第1章 地方自治の現在一中央集権化と地方自治との対抗 …岡田知弘
第Ⅱ部 国の自治体に対する「補充的指示権」をめぐつて
第2章 「特権的指示権」にみる「逆分権化」の危険な徴候……自藤博行
第3章 感染症対策と補充的指示権一新型コロナウイルス感染症対策に関わる立法をふまえて ……松田亮三
第Ⅲ部 公共サービスをめぐる政策変化と自治体間違携・公共私連携
第4章 情報システムの「最適化」と地方自治一個別最適から全体最適へ…………………………………本多滝夫
第5章 公共サービスをめぐる自治体間連携………………平岡和久
第6章 公共私連携のあり方………………河合克義
第Ⅳ部 地方自治の未来像
第7章 地方自治の未来像………・…榊原秀訓
準新刊紹介
公園の木はなぜ切られるのか
●市民の拠り所で木が切られ、稼ぐ場所へと変容!
A5判 並製 64頁 定価900円
尾林芳匡・中川勝之著
明治神宮外苑の再開発計画が進んでいます。再開発により、外苑の樹木の大量伐採につながるのではないかと、各方面から批判の声が上がっています。故・坂本龍一を初め、桑田佳祐、村上春樹らも反対意見を表明しています。実は、このように「公園の木が切られる」事態は日本全国で起こっています。
自治体、行政が市民のために公園を維持するよりも、「稼ぐ公園」へとシフトしているのです。そこには「公園PFI」という手法を用いて、民間企業を取り込み、都市公園の民営化、産業化の動きがあります。大阪、埼玉、東京、静岡、長野、兵庫の実例を取り上げて、都市住民の拠り所である公園をどのように守っていけばよいのか、考えます。
目次より
第 1 章 外苑の森が危ない 明治神宮外苑の森が危ない/外苑の森が大きく変わる再開発計画/東京都が旗振り規制緩和/ 第 2 章 全国で広がる公園 PPP/PFI の動きと概観 都市公園はいま/都市公園法のあらまし/公園 PFI(Park-PFI)の導入のいきさつ/2017 年都市公園法改正と「稼ぐ公園」/ 第 3 章 PPP/PFI とは PPP/PFI とは/PPP/PFI が進められてきた背景/自治体民営化を進める制度とその特徴/第 4 章 公園をめぐる全国の事例 大阪市・「木を切る改革」と「稼ぐ公園」/さいたま市・与野中央公園/京都府・北山エリア/東京都・日比谷公園/静岡市・城北公園/長野県須坂市・臥竜公園/
■自治体研究社 〒162-3512新宿区矢来町123矢来ビル4F
tel:03-3235-5941/fax:03‐3235‐5933
http://WWW.jichiken.jP/ E‐Mall info@jichiken.jp
巨大再開発、DX・GX で 東京のまち・自然が破壊される
徹底検証!東京都政
発行:旬報社 定価1700円+税
山本由美・久保木匡介・川上哲・一般社団法人 東京自治問題研究所 編著
第1章 都政は何を進めてきたのか ―国際競争力強化と巨大再開発
第2章 加速する都市再開発と住みにくくなる東京
第3章 DX・民営化による 公教育・保育の変質
第4章 社会保障、医療、公衆衛生、ジェンダー
■東京自治問題研究所 fax03-5976-2573
電話 03-5976-2571
E-mail tokyo-jichiken@clock.ocn.ne.jp
以上、「月刊いばらきの地域と自治」第186号から転載
------------------------------
主要ページのご案内
→月刊「いばらきの地域と自治」最新号をどうぞ;NEW!
先月以前のものはこちら→月刊「いばらきの地域と自治」既刊号すべて
過去のスクラップは→過去の自治関連ニューススクラップ
------------------------------
a:112761 t:12 y:28