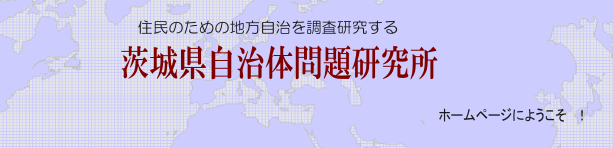第167号
第167号
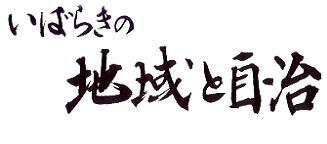
第167号
2022・11・22更新


泉坂下遺跡=常陸大宮市泉
泉坂下遺跡は、常陸大宮市泉にある弥生時代中期(約2,300~2,200年前)の再葬墓遺跡です。泉坂下遺跡から出土した人面付壺形土器をはじめとする56個の土器と副葬品の遺物61点は、平成29年、国重要文化財に、同年、遺跡は国指定遺跡に指定されています。出土品は、常陸大宮市民俗資料館で展示されています。
〒319-2144 茨城県常陸大宮市泉 。
************
マイナンバーカード事実上の強制、国会で審議を
守谷市は、0~18歳の市民がマイナンバーカードを使って市の公式アプリから申請すると、市内の店舗で使える1万円相当のポイントを付与すると発表。カードの普及を促す狙いがある。国が来年度から、地方に配る地方交付税の算定にカードの交付率を反映させるとの方針が自治体を突き動かしている。
河野デジタル大臣は、2024年秋に現在の保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化する方針を示し、任意のはずのカードを事実上義務化することに踏み切った。
稲葉一将教授(名古屋大大学院)は指摘している(11月16日 朝日新聞)。
「ポイントは二つです。まず、カードを普及させる目的は国民の利便性の向上です。保険証を廃止してカードのみにすることが利便性向上と言えるのでしょうか」
「次に、本人確認の手段としてカードに魅力を感じたから、自分の意思で申請するというのが任意性です。任意であるはずのカードを持たないがゆえに、不便を感じるような生活環境をつくることは、申請を事実上強いるもので法律の趣旨に違反する恐れがあると言えます」。
さらに、「国民主権や民主主義の観点からは、私たちが代表を送る国会での審議が重要になります。しかし今回はそうではなく、デジタル大臣が見解を発表しただけで、閣議決定ですらありませんでした。1人の有力な人物が発言し、それで物事が進んでいく状況は、法治主義や民主主義、国民主権の危機だと言えます」
個人情報の国家による一元的管理への不安・不信が取り除かれる十分な説明もなく、あの手この手で国民や地方自治体を追い込んでいく政府・担当大臣の手法には賛成できない。
稲葉教授の新著『ジタル改革とマイナンバー制度 情報連携ネットワークにおける人権と自治の未来』(自治体研究社)が問題を考えるうえで役に立ちます。
************
今月の俳句
大利根の川面明るく夕時雨
田をめぐる畔(あぜ)乾きをり落とし水
虎落笛(もがりぶえ)老し夫婦に会話なし
人はみな帰る家持ち小夜時雨
駅の名に昔を偲び帰り花
鳥渡る過疎も都会もない空を
古井戸の残る民家や雁渡る
高 島 つよし
本名 高島剛 常総市在住、句歴七十年 元茨城県職員 元小貝保育園長、当研究所顧問
寄 稿
北茨城の海と漁業をまもるために
穂積 建三( 大津漁業協同組合の永山さん、鈴木さんを支える会共同代表・当所理事)
―大津漁協の不当解雇は許さないー
北茨城市大津漁港の週末は、県内・福島・群馬・栃木などから来た数百台もの車と釣り人でいっぱい。大津漁業協同組合に勤めていた永山孝生氏は、祖父の代から地元の漁師の家で生まれ、海と漁業を守るために自主的に港を清掃するなど頑張ってきました。また、鈴木基栄氏は、「漁協は地元に貢献できる職場」と思い、意欲的に働いてきました。
その二人が今年2月に解雇され、水戸地裁で闘っています。
二人はなぜ解雇されたのか
大津漁協の一部幹部が原発事故後による魚介類の放射能数値について、基準値を超えた数値を基準値内に改ざん。内部でそれを指摘してきた永山氏が「虚偽情報をリーク」したとか、幹部のパワハラによる心身障害で出勤できなくなった鈴木氏を「業務に耐えられない」として解雇したのです。
裁判が始まりました
裁判は、7月1日に口頭弁論で始まり、現在まで4回。第5回は12月23日(金)です。
毎回、水戸地裁(3階)第3法廷は「支える会」はじめ支援労組団体の皆さんで満席。被告は、原告が主張した解雇無効の論点に反論できず、退職金を上乗せすることで解雇を容認するように論点をすり替えたり、被告席に座った漁協役員が原告を揶揄する不規則発言を繰り返して裁判長から強く注意されています。
終了後は、生涯学習センター講座室で、原告、弁護士を交えて当日の論点を深めています。
警察や会計検査院も動き始めた
水戸地裁で第4回口頭弁論が行われた10月28日の朝、県警は詐欺容疑で大津漁協の事務所を家宅捜索しました。原告たちが以前から職場で指摘し、改善を求めてきた不正な会計処理に警察や会計検査院のメスが入ったのです。
雇用調整助成金を不正受給
新型コロナウイルス対策で、従業者に支払う休業手当を国が補塡する雇用調整助成金(雇調金)を不正受給したのです。
2020年、直営市場食堂の従業員が出勤したにもかかわらず、新型コロナの影響で従業員が休業したと虚偽申請し、雇調金をだまし取った疑いです。不正受給額は少なくとも数百万円規模で、漁協幹部は不正受給を認めています。
製氷工場の修復費2千万円分「不当」
国の予算の使われ方を調べる会計検査院によると、大津漁港の製氷工場が東日本大震災で被災し、国からの補助金で修復しました。
しかし、建物全体が傾いて機械が故障するなどの影響で使用を断念し、新たに別の製氷工場を建て直しました。補助金2000万円余りが目的どおり使われなかったと指摘しました。
地元で市民シンポジウム開催へ
北茨城の海を守る会・大津漁協の永山さん・鈴木さんを支える会は、裁判の経過を報告し、今後の展望を語り合う「市民シンポジウム」の開催を予定しています。
1 日 時 12月18日(日)午後1時30分
2 ようそろ ー 伝承室(北茨城市漁業歴史資料館)
************
事務局たより
緊急「自治体問題研究所維持のための1000万円カンパ」のお願い
自治体問題研究所より下記のとおり「カンパのお願い」要請があり、10月8日開催の茨城県自治体問題研究所第2回理事会で議論の結果、当研究所会員のみなさんにもご協力を呼びかけることとなりました。
2022年9月25日
自治体問題研究所会員各位
自治体問題研究所 理事長中山 徹
前理事長岡田知弘
(株)自治体研究所 代表取締役 長平 弘
緊急「自治体問題研究所維持のための1000万円カンパ」のお願い
これからの政治と行政を大きく左右する沖縄県知事選は、玉城デニー氏の再選勝利に終わり、一方では安倍元首相の国葬などをめぐり岸田内闇への支持が急落しております。
これからの動きに注目したいと思います.
さて、自治体問題研究所と自治体研究仕の経営は、みなさまからの会費と学習会などでの単行本の売り上げに支えられてまいりました。しかし、いまだ出口の見えないコロナ禍によって.学習会や著者の講演会などが十分復活できず、図書販売も従前の売り上げを回復できておりません。そのため私どもでは、「市町村議員研修会(Zoom開催)」を全国37の地域研究所のご協力で定期開催することで収入増を図るとか、年明けより『住民と自治』の価格改定を日指す方向で議論を重ねております。
しかし、毎月200万円超の収入不足を取り返すことは並たいていのことではありません。
そこで、すでに「サボーター制度」の名によるカンパをお願いしており、再度のお願いで恐縮ですが、2022年9月~12月の間に、総額1000万円を目標額として、研究所維持のための緊急特別カンパを以下の要領で呼びかけさせていただくことといたしました。
自治体問題研究所は60年にわたり、地方白治・住民自治を守り発展させるためその役割を果たしてまいりました。この灯を消すことなく、いままた軍拡や「自治体DX」の名による地方制度の大きな改変が企図されるとき、情勢に応えて情報を発信し続けてまいりたいと考えております。ご協力いただければ幸いに存じます。
記
〇特別カンパの目標額 1000万円
〇特別カンパの期間 2022年9月~12月
〇特別カンパの申込み金額 1口1万円 (何ロでも)
〇振込口座 郵便振替口座番号 00100-7-170408
名義:自治体問題研究所
※ ご協力頂ける方は茨城県自治体問題研究所事務局までご連絡ください。電話:029-252-5440
自治体問題研究所の緊急財政カンパのための資料
<財政状況について>
●コロナ禍と物価高による急速な財政状況の悪化
・コロナ禍で事業ができなくなったり、大幅に縮小せざるを得ない状況となった
・事業収入および活動の中心となってきた書籍販売が大きく落ち込んだ
書籍の発行点数は2019年15点から2021年には16点へと増やし努力をしてきたが
売上額は1200万円以上の減少となった。(集会、著者講演会などの行事減少)
・今年春以降の印刷費等の高騰による、諸経費の増加
9月までに既に2回の値上げが実施されている
・昨年までのコロナ関連融資等ができなくなった
●構造的な赤字
・長期にわたる会員減少(高齢化、労働組合)
<当面の対応>
●自治体問題研究所を維持するための財政見直し
・会員拡大、「住民と自治」読者の拡大
・「住民と自治」の構造的な改善
現在の定価の見直し
製造原価、全国研配分、地域研配分についての検討
・事務局体制の見直し
「住民と自治」の編集体制の見直し
その他人件費
・全事業の見直し及び事務費の見直し
・事業収益の増加(市町村議員研修会等)
・出版事業の見直し改善 刊行点数は維持
コスト削減、出版部数、刊行時期の平準化、広報、編集体制見直し
<成長期間>
●来年度以降の見通し
・会員拡大の推進
・Zoomを活用した各種の学習会、読書会
・録画ライブラリーの活用
・地域研のZoomイベントの活用
・全国研WEBサイトの改善
●自治体問題研究所と自治体研究社の関係整理
今月の 川柳
ていねいに又丁寧に嘘をつき
地球危機暗示するのか赤い月
防衛費ブレーキ効かず焼け太り
過疎の娘の心をつなぐローカル線
第八派コロナたまげて出るくしゃみ
アベコベに物が動いている政治
大臣は判こひとつでくずれ落ち
水力があるじゃないかと電気屋さん
味覚秋シワの数ほど値が上がり
錦秋の腹いっぱいに紅葉食べ
泉 明 羅
(泉明羅・本名 福田正雄 水戸市在住、句歴 四十二年、所属 元吉田川柳の会)
❀❀❀❀❀❀❀❀
新刊紹介
生まれる前から、子育て・教育の枠を超え「子どものデータ」が収集・利活用される ‼
『保育・教育のDXが子育て、学校、地方自治を変える』
稲葉 一將, 稲葉 多喜生, 児美川 孝一郎 著
A5判 98頁 定価1100円(税込み) 2022年 11月10日発行
'概 要:'
デジタル改革によって、子どもの個人情報が大量に収集、集積、利活用される仕組みが準備されている。
本書では、Ⅰこども家庭庁の設置を前に、複数の行政組織や自治体の部局を超えて「こどものデータ」が連携・集積される構図とその意味すること、Ⅱ保護者と保育園をつなぐ保育支援システムによってこどものビッグデータがテック企業に集積される仕組みとその意味すること、 ⅢGIGAスクール構想の先ですすむ「教育DX」政策が公教育にもたらすものを整理する。「こどものデータ」の収集と利活用は、子ども像を変えるだけでなく、子育て・教育に携わる専門職の存在や自治体行政の姿を変えることにつながる。
主な内容
Ⅰ 子どものデータ連携と行政組織における調整の強化―こども家庭庁新設の地方自治への影響……稲葉一将
国家によって形成される「デジタル社会」の特徴/子どもと行政に及ぶ「デジタル化」/転形期の子どもと行政
Ⅱ 保育業務のSaaS化とテック企業のデータ寡占―保育と一体で行われる子どもデータの収集……稲葉多喜生
SaaS で行われる保育データ収集の意味すること/企業任せとなっている個人情報収集/便利さの背後で進む、テック企業のデータ寡占化/子どものデータ連携で変わる保育
Ⅲ 教育DXが学びと学校を変える……児美川孝一郎
「Society 5.0 型教育改革」の構想―EdTech を通じた教育 DX の実現へ/GIGA スクール構想とコロナ禍の教育政策/教育 DX は学びと学校をどう変えるか
準新刊
子どもを真ん中に考える!
学童保育を哲学する ―子供に必要な生活・遊び・権利保障―
増 山 均 著
A5判、150頁 定価1870円 自治体研究社
コロナパンデミックのなか、学童保育の社会的役割が増しています。そこにはさまざまな運営主体が参入し多くの人々がかかわっています。いま「学童保育とは何か」「学童保育はどうあれば良いのか」という≪理念の確認≫が必要な時です。子どもの生活と遊び、権利保障のあり方、地域との連携,子ども観など、子どもを中心に置いて問題を熟考(哲学)します。
『健康で文化的な生活をすべての人にー憲法25条の探求』
浜岡 政好, 唐鎌 直義, 河合 克義 (編著)
A5判 308頁 定価2970円(税込み) 2022年3月31日発行
概要:人間らしい生活を求めて
格差と貧困が拡大する今、私たちは「健康で文化的な生活」を送れているのでしょうか。全国生活と健康を守る会連合会と全日本民主医療機関連合会による大規模アンケート調査から庶民の肉声を掬い上げました。そこには、さまざまな生活を送る人びとの日常があります。
このデータの多角的な分析と、第2次調査としての面談による取材によって、日本の庶民の現実が見えてきます。また、「健康で文化的な生活」とは何かを、憲法25条の文言の成立からたずね、フランスとの比較も通して、「人間らしい生活」を求めて、社会保障・社会福祉の低位性を乗り越える方策を追究します。
コロナ対応にみる法と民主主義
コロナ禍とデジタル化のもと見つめ直すべきは民主主義と地方自治のあり方である
市橋克哉・榊原秀訓・塚田哲之・植松健―著 定価1,870円
概要:
コロナ禍とデジタル化のもと、パンデミックに便乗して、立憲主義・法治主義を掘り崩す政策が頻発した。国家は人びとの「命と暮らし」を一番に考えていたのか。地方自治体、地方議会は、その役割を十分に果たすことができているのか。さまざまな事実を法と民主主義の観点から詳細に分析して地方自治と民主主義の可能性を追究する。
社会保障のあゆみと協同
社会保障の枠組、歴史、さらに協同との関係性を紹介
芝田 英昭著 (立教大学コミュニティ福祉学部教授)
A 5 判・並製カバー・160 頁/定価1870 円(10% 税込)
本著の概要:
社会保障は、私たちが生きていく上で必ず抱える生活問題を緩和・解決するための公的な制度・政策や協同の取り組みです。その目的は、全ての人の「健康で文化的な生活を保障」するもので、
健康権・文化権・生活権等の基本的人権を保障する制度だといえます。しかし、基本的人権は、戦争ではしばしば侵害されます。
平和であることが社会保障の発展にもつながり、また社会保障の発展が平和に貢献できるともいえます。本書では、社会保障の基本的枠組、歴史、さらに生命の尊厳、協同の力・運動・実践と社会保障発展との関係性を学びたいと思います。 (本書「プロローグ」より)
危険!建設残土 - 土砂条例と法規制を求めて
熱海土石流事故は、あなたの身近でも起りうる!
畑 明郎著 (滋賀環境問題研究所所長、日本環境学会元会長、元大阪市立大学教授)
定価1650 円(本体1500 円+税10%)
本著の概要:
2021 年7 月、熱海土石流事故は建設残土問題をクローズアップした。同じように全国には、持ち込まれ、積み上げられる危険な建設残土が多数存在する。熱海市をはじめ、京都、滋賀、大阪、奈良、愛知、三重の現状を精査して、その危険性を報告する。
そして、大量の残土を生み出す、北海道・北陸新幹線の延伸工事、リニア中央新幹線工事の問題点を明らかにする。
こうした現実に対して、土砂条例と実効性のある法規制の必要性を説く。
どう考える 公共施設の統廃合・再編、民間化
―公共施設等総合管理計画と指定管理者制度―
角田英昭 編著
A5版・32頁 地域研割引単価300円(定価400円)
現在、公共施設の統廃合・再編が急ピッチで進められています。
その基軸となるのが公共施設等総合管理計画です。この計画は、これまでのような自治体による個別、施設ごとの統廃合・再編に止まらず、中長期的な視野に立って全面的に見直し、施設の総量削減、経費抑制を国主導で推進していくものです。
また、公共施設の管理・運営については、国は指定管理者制度を先行して実施し、管理運営委託、民間化を全面的に推進しています。総務省資料によれば既に7万7千超の施設に導入されていますが、実際の運用では、指定取り消し等が過去最高を更新するなど様々な問題、課題が指摘され、その見直しは急務になっています。
改めて公共施設とは何か、どうあるべきなのか、それが根本から問われています。 「公の施設」とは、住民のライフサイクル全体を通して福祉の増進を図り、地域の社会経済活動の基盤をつくり、まさに自治体の仕事の根幹をなすものです。
こうした状況を踏まえ、今回、自治体問題研究所では公共施設のあり方、統廃合・再編、民間化を考えるブックレットを作成しました。今年3月に公表された2021年「公の施設の指定管理者制度導入状況等調査」の概要も掲載しました。是非お読み頂き、地域、職場での学習と政策づくり、運動に役立てていただければ幸いです。
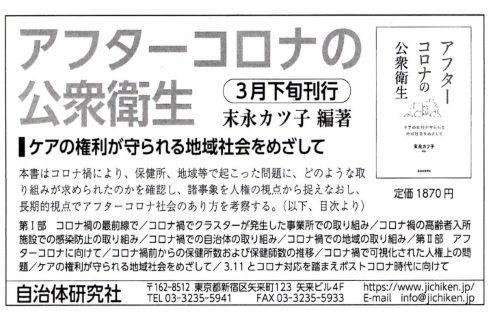
戦後最大の国民生活の危機!コロナがあばいた日本の弱点!
伊藤周平著『コロナ禍からみる日本の社会保障』
定価 2200円
オミクロン株が猛威を奮い、まさに第6波の真っ只中である。コロナ禍の収束は見通せず、日本の社会保障の制度的脆弱さは深刻化を増している。医療・保健(公衆衛生)、介護、保育・学童保育、雇用保障、生活保護・住宅政策等の実際を論じ、社会保障の法政策と税制改革を中心に財政政策の方向性を提示する。
デジタル化でどうなる個人情報
デジタル改革と個人情報保護のゆくえ
ー「2000個の条例リセット論」を問う ―
庄村勇人(名城大学法学部教授)・ 中村重美(世田谷地区労働組合協議会議長)著
定価990円(10% 税込)
デジタル改革関連法の成立により、住民の個人情報は“利活用"する方向が示され、個人情報保護条例は国の法律に合わせて「改正」を強いられ、その監督権限も国に一元化される方向へと動きだした。本書では、地方自治の視点から、デジタル改革関連法における個人情報保護法制の内容を検証するとともに、住民の権利と団体自治を守るための自治体の課題や条例の論点を具体的に考える。
福島原発災害10年を経て
ー 生活・生業の再建、地域社会・地域経済の再生に向けて ー
鈴木 浩著
A5/258頁 定価(価格3200円+税)
東日本大震災・福島第一原子力発電所事故による原発災害から10年が経った。被災者の生活再建と、被災地の地域社会の再生はどこまで進んだのか。災害発生直後から福島県と浪江町、双葉町の復興ビジョンや復興計画の策定、そして仮設住宅の供給についての計画づくりに関わり、「ふくしま復興支援フォーラム」を立ち上げた著者が、被災者、被災地そして自治体のいままでの取組みとこれからの方策を語る。10年は決して区切りではない。再建、再生の実際を問う。